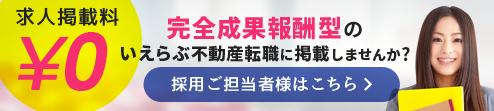建築士の資格にはどのようなものがあるの?その違いや年収も知る
目次
今回は建築業界への転職を検討している方に向けて、役立つ資格についてご紹介していきます。
種類やその取得方法、また違いと年収についてもみていきましょう。
どのような人に向いているかなどもご紹介していきます。
建築士になるための資格とは
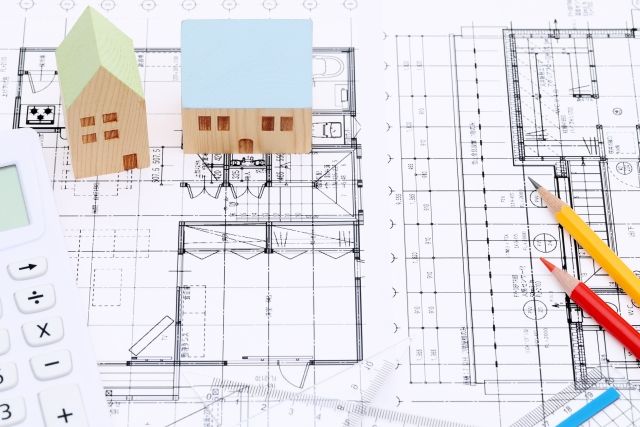
まずは概要についてご紹介していきましょう。
建築士とは、建物の設計や工事の管理などをおこなう職業です。
取り扱う建造物は、高層ビルやマンション、病院などの施設や、一軒家などさまざまです。
仕事内容としてはまず「設計」があります。
建築基準法とよばれる法律を守り、建築物の設計をおこなう業務です。設計を図面に書き起こした設計図が重要で、建築物の基盤になってきます。
建築物の用途やイメージをヒアリングする業務からはじまり、建築予定地の法規制なども踏まえたうえで最適な建築方法や内装のイメージをすりあわせる業務です。
設計図だけでなく建物のミニチュア模型を作成し、打ち合わせを重ねることもありますよ。
次に「工事監理」です。
工事監理とは、実際に進んでいる工事が設計図通りに進んでいるのかを確認することを言います。
建築工事をはじめ、ほとんどの工事は工程が始まる前に設計図が作成されます。
その設計図通りに工事が進んでいるかを確認するために、工事監理者は
・設計図に基づいた施工が行われているか、設計図と照合
・進行する段階で設計者に質疑という形で確認
をすることになります。
最後には報告書の記載をおこない、報告する業務もあります。
また、工事に関するコスト管理も担当になります。
資格には一級建築士と二級建築士、木造建築士の3種類があります。
資格によって扱える建物の範囲が異なっており、一級はその範囲がもっとも広く、次に二級、最後に木造となっています。
<資格をとるにはどうするか>
資格を取得するには、建築に関する学科がある大学や専門学校で学ぶのが一般的です。
一級はこれまで、試験を受験するためには指定科目を修めて卒業したあと、数年の実務経験が必要でした。
しかし「建築士法一部を改正する法律」により、令和2年の3月大学卒業者から、実務経験がなくても受験が可能になっています。
ほかには二級建築士や建築設備士として、実務を4年以上の経験をしていれば、それも一級の受験資格となります。
二級と木造の試験における受験資格は、大学や短期大学、高等専門学校・高等学校・中等教育学校において指定科目を収めて卒業した者です。
または実務経験7年以上の場合も受験資格となります。
建築士になるための資格の違いとは

次に一級・二級の違いについて詳しくみていきましょう。
試験の難易度は一級で12%、二級で22%程度といわれており、一級のほうがやや難しい傾向です。
仕事内容の違いとして、一級は住宅以外に体育館や学校、ドームなど公共建築物も設計ができます。
二級を取得している方の多くは住宅を専門に設計しています。
世間には小規模な住宅のほうが建築物として数が多いので、住宅設計の専門家としての知識を得られるメリットがありますよ。
それでは建築士に向いている人はどのような人なのでしょうか。
まず一級に向いている人は、大規模な設計や国家的なプロジェクトなどに携わりたいと考える方です。
また国際的な建築して活躍したいと考える場合にも、一級の取得が向いているでしょう。
さらに建築業界で仕事をしたいと考えている場合、建築の一般企業では商業施設や公共施設の設計をおこなっているため、一級が必要になります。
次に二級に向いている人は、戸建て住宅など住宅専門で設計したいと考えている方です。
大規模な建築物の設計では、多数のお客様を想定して設計をおこないますが、住宅設計の場合、一人一人のお客様と直接のやりとりを必要とします。
お客様のことを丁寧に考えながら設計をおこないたいと考えている方は、二級に向いているのではないでしょうか。
また二級を取得して実務経験も積めば、一級へとステップアップも可能です。
どのような建築士として活動したいか、また違いも含めて検討してみてくださいね。
<木造建築士とはどのような資格か>
木造建築士は木造住宅の設計をおこなうための資格です。
試験の受験資格は二級と同じですが、難易度は二級よりも少し低く、合格率は33%ほどといわれています。
仕事内容としては、二階建てまでの木造の建物が設計できます。
木造以外の住宅や、ビルなどの大きな建築物の設計はおこなえません。
一級・二級と比較すると取得しやすいといえそうです。
しかし木造建築士は木造住宅のスペシャリストであり、一級や二級と同じ国家資格です。
木造建築物の専門的知識をもつので、木造建築物の設計や建築工事はもちろんのこと、歴史的建造物の維持などの仕事をしたいと考える方には、向いているといえるでしょう。
また一般的な住宅のみでなく、指定範囲内の大きさの建築物であれば、店舗や公共施設に携わることも可能です。
ぜひ検討してみてくださいね。
建築士の資格を得て就職した際の収入はどのくらいか

有資格者の転職の際は収入に注目するのではないでしょうか。
年収は一級だと600~700万円、二級だと440~520万円くらいといわれています。
また就職先の業種によっても収入は前後してくるようです。
ゼネコンや建築会社、ハウスメーカーや設計事務所などが就職先として検討されると思われます。
そのなかでも比較的ゼネコンは年収が高く、設計事務所とは50万ほど差があると予想されるようです。
もちろん会社規模や経験の差によって変わりますので、決めつけることはできません。
また大学卒や短大卒、高卒などの最終学歴でも年収に差がでる傾向です。
どの学校をでても年齢が上がるとともに年収も比例して上がりますが、この最終学歴の差が50歳の時には数百万円もの年収の差になる場合もあります。
地域によっても年収は変動してきます。
東京都はもっとも高く、ついで大阪・愛知・福岡・北海道の平均年収が高いようです。
こちらも時代や世間の経済状況とともに変化する項目なので、あくまでも参考となります。
ボーナスも会社や経験によって変わりますが、およそ73万円と予想されています。
収入を高くしたい方は、比較的二級よりも一級をもっている方のほうが高くなるようです。
また最終学歴も大学卒のほうが、高い傾向にあるでしょう。
なかでも大手ゼネコンなどは比較的年収が高い傾向です。
もちろん業務内容も重要な項目ですので、収入だけにとらわれず生活スタイルも踏まえて検討する必要があるでしょう。
<建築士の資格を取得して独立するとどうなるか>
建築士は独立して自分の事務所を開業したり、フリーランスとして働いたりすることも可能な職業です。
戸建て住宅を専門に手掛ける方や、デザイナー的な働き方をする人など、人それぞれの働き方があります。
もし独立を考える場合は、建築士としての能力以外に経営者としても働くことになります。
仕事が入ってくる保証がないため、働き方としてのリスクは高くなるでしょう。
また資格を取得したからといって、すぐに独立するのは難しいと考えられています。
企業などで実務スキルを身につけ、知識を得るのが大切なようです。
また開業にあたっては「管理建築士」の保有者が必要になります。
この資格の取得には実務経験や指定登録講習が必須なので、準備をしましょう。
開業資金も必要になりますね。
また収入に関しても人それぞれで、差がみられます。
年収1,000万円以上を得ている方もいますが、200~300万円の方もめずらしくありません。
個人のスキルや定期的な受注の入る環境があるかなどで、収入は大きく変わってきますので、あらゆる状況を覚悟しておく必要がありそうです。
まとめ
建築士の資格についてまとめました。
3種類それぞれに特徴や違いがあり、また働き方も多少変わってくるようですね。
ご自身の理想とするライフスタイルも踏まえたうえで、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
このコラムを書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。
カテゴリ一覧
タグ一覧
人気記事ランキング
ピックアップ求人
いえらぶ不動産転職のおすすめ求人情報をピックアップしてお届けします。

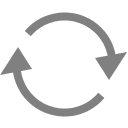


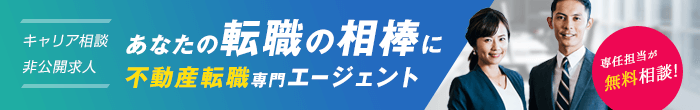










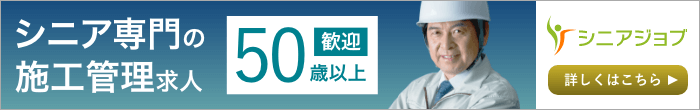


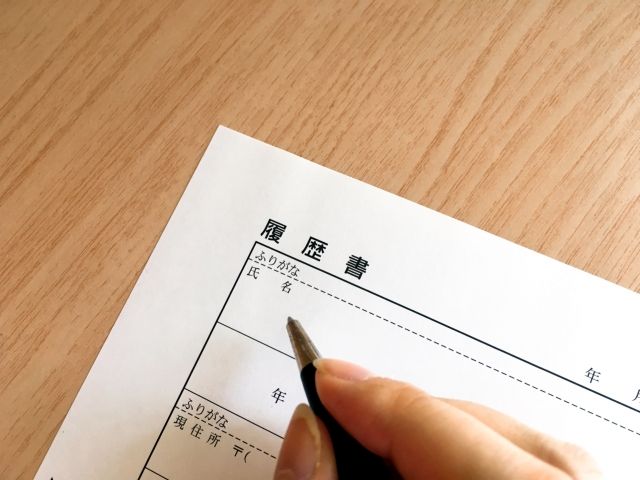





 10:00~18:00(日曜、年末年始を除く)
10:00~18:00(日曜、年末年始を除く) で相談する
で相談する